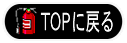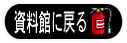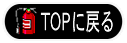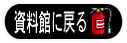|
●台風とは
台風(颱風)とは、太平洋や南シナ海(赤道より以北、東経180度より以西100度より以東)で発生する熱帯低気圧で、最大風速(10分間平均)が34ノット (17.2m/s)以上のものを指す。
WMO(世界気象機関)による国際分類の定義では、日本の台風とは異なり、最大風速(1分間平均)が64ノット以上のものをタイフーン(typhoon)と呼ぶ。
ちなみに、WMO(World Meteorological Organization)は、国際連合の専門機関の一つで、気象観測業務の国際的な標準化と調整を主な業務としている。
WMO国連と連携はするが、あくまで別の機関であり、国連に参加していない国でも加盟できる。
台風が、国際分類上、熱帯低気圧をハリケーンやサイクロンと呼ぶ区域に進んだ場合には、台風ではなくそれぞれの区域の名称で呼ばれることになる。
東経180度より東(西経)に進んだ場合、最大風速(1分間平均)が64ノット以上のものはハリケーンと呼ばれ、34ノット以上64ノット未満のものをトロピカルストーム(Tropical Storm)と呼ばれる。
また、マレー半島以西に進んだ場合、サイクロンと呼ばれる。

●台風の大きさと強さ
台風の勢力を分かりやすく表現する目的等から、台風は「強さ」と「大きさ」によって分類されている。
強さによる分類は、国際的にはWMOが規定する分類法が使用されているが、それに準じた多少差異のある分類法もいくつか使用されていて、同じ台風でも気象機関によって異なるレベルに分類される場合がある。
具体的には、米軍の合同台風警報センター(JTWC)では1分間平均の最大風速、日本の気象庁では10分間平均の最大風速によって分類する。
例えば同じ台風の同時刻の観測において、米軍の合同台風警報センターがtyphoonの強度に達したと判断しても、日本では強い台風の強度に達せず並の強さと判断する場合も生じる(1分間平均風速は10分間平均風速よりも1.2〜1.3倍ほど大きく出る傾向にある)。
なお現在日本では、観測員や設備・運用等の負担が大きい台風の航空機観測は行っておらず、過去の観測データの蓄積により確立されたドボラック法に基づいて、台風の衛星画像から台風の位置、中心気圧、最大風速、大きさの数値を算出している。
また、現在は最大風速で強さを分類しているが、以前は中心気圧が用いられており、その慣習から日本では台風情報に中心気圧も併せて発表される。
【強さの階級分け】
| 最大風速 (m/s) |
�最大風速 (knot) |
国際分類 |
日本の分類 |
| (旧) |
(新) |
�
| <17.2 |
<33 |
Tropical Depression (TD) |
弱い熱帯低気圧 |
熱帯低気圧 |
�
| 17.2 - 24.5 |
34 - 47 |
Tropical Storm (TS) |
�台風 |
弱い |
台風 |
|
| 24.6 - 32.6 |
48 - 63 |
Severe Tropical Storm (STS) |
並の強さ |
| 32.7 - 43.7 |
64 - 84 |
Typhoon (T) |
強い |
強い |
| 43.7 - 54.0 |
85 - 104 |
非常に強い |
非常に強い |
| >54.0 |
>105 |
�猛烈な |
猛烈な |
日本の気象庁は、大きさによる分類も行っている。
風速15m/s以上の強風域の大きさによって分類する。
15m/s以上の半径が非対称の場合は、その平均値をとる。
なお、以前は1,000ミリバール(現在使用されている単位系ではヘクトパスカルに相当)等圧線の半径で判断していた。
【大きさの階級分け】
| 風速15m/s以上の半径
| 大きさの階級
|
| (旧) |
(新) |
| <200 km |
ごく小さい |
|
| 200 - 300 km |
小型(小さい) |
| 300 - 500 km |
中型(並の大きさ) |
| 500 - 800 km |
大型(大きい) |
大型(大きい) |
| >800 km |
超大型(非常に大きい) |
超大型(非常に大きい) |
これらを組み合わせて、かつては「大型で並の強さの台風」というような言い方をしていた。
しかし、組み合わせによっては「ごく小さく弱い台風」となる場合もある。
1999年(平成11年)8月14日の玄倉川水難事故を契機に、このような表現では、危険性を過小評価した人が被害に遭うおそれがあるとして、気象庁は2000年(平成12年)6月1日から、「弱い」や「並の」といった表現をやめ、上記表の(新)の欄のように表現を改めた。
したがって、「小型で『中型で・ごく小さく』弱い『並の強さの』台風」と呼ばれていたものは、単に「台風」、「大型で並の強さの台風」は「大型の台風」と表現されるようになった。
|